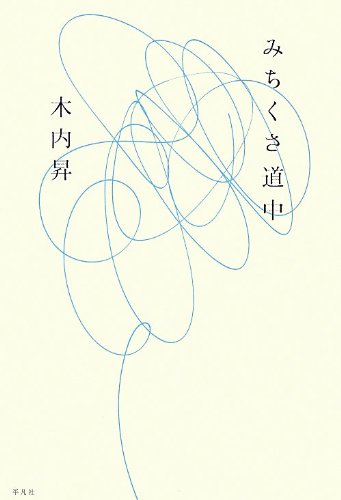木内昇 座談会@早稲田大学
早稲田大学で行われた作家の木内昇さんの座談会に参加してきた。
普段小説はすすんで読むほうではない。読むとしたら大抵誰かが褒めていたり、薦めていたら読むことにしている。
これまでだと、たとえば椎名林檎が三浦綾子の「氷点」やコクトーの「恐るべき子供たち」に影響された、と雑誌に書いていれば読んだり、幾原邦彦監督が辻村深月の「鍵のない夢を見る」がいい、といえば探して読んだり、と小説との付き合いはどちらかというと受け身である。
木内さんの存在を知ったのは購読している新聞の夕刊のコラムだった。昇、という名から最初は男の人なのだろうか、と作者を想像しながら読んでいたもののどうやらそうではない、と気付いたのは連載が後半に入ってからだった。
時に行き過ぎた妄想をし(妄想的活躍譚)、時に誰にも言えない寂しさを分析する(寂しさの考察)。テンポの良い文章の中にぐいぐいと引き込まれ、読み終えた後には名残惜しく、また読みはじめてしまう。文章から想像する木内さんは見た目は細くとも(テンポの良い文)芯の通った漢(いうべき所はハッキリいう)だった。(女性ではありますがあえて「漢」が似合う人とさせていただきます)
同じような経験を向田邦子の小説にもあったけれども、ツボに入る文とはこういうものを言うのだな、と毎週の夕刊を楽しみにしていた。
新聞の連載は6カ月。最後のエッセイを読むのは当然寂しかったのだけれど、あっさりと連載は終わった。「また、どこかで逢う日まで」と書かれていたが、不思議と喪失感はなく、著書を買えば彼女の文を読むことができるのだな、と前向きにとらえていた。
連載が終わるまでに木内さんの著書はあえて読まなかった。木内さんは時代小説という固いイメージのある小説を中心に書いていてとっつきにくさがあったこと、そして、エッセイと小説は別物であり、エッセイほど面白くなかったらいやだな、という理由だった。
けれども、どの本もそれぞれ面白く、結果的にほとんどの本を読んで今に至る。登場人物がいきいきとしている。彼らは決して目立つような人ばかりではない。いってしまえば今でいうと「一般の人」とされてしまう所を、丁寧に書く。それゆえ文章に引き込まれ、心動かされるのだろう。
前置きが長くなったけれど、今回の座談会は最新作「櫛挽道守(くしひきちもり)」という櫛職人を主人公にした物語を中心に、担当編集者の方を交えた話だった。
小説の内容についてのやりとりはいくつかありましたが、未読の方もいると思われるので割愛します。
***
●時代小説を題材とする理由
・もともと学生時代に山本周五郎などの本に触れており、時代小説に対する抵抗はなかった。
・時代ゆえに様々な制約はあるものの、移動手段が限られていた分、人が狭い範囲の中で踏みとどまって生活していた。そのため密な人間関係を書くことができる。
・職業によって体つきの違いがはっきりしていた。それゆえ、相手の心情を描かなくても、体つきで表現できる(直木賞受賞作の「漂砂にうたう」にも幾つもちりばめられている。)
・住む場所が固定化されたり、情報が得られる手段が限られると、情報共有できていないこと各人物の背景につながり、それが物語に深みを与える。
・今は情報をすぐに得られたり、他人の意見を得ることができたり便利ではあるが、「考えるための時間」が少なくなっているように感じる。
●登場人物の作り方
作者や話の流れによって登場人物の動きを変えない。それよりも、「この人だったらどういう行動をするのか」、を考える。あくまで主体は登場人物の性格。
自費雑誌を発行していたころの経験が役に立った。
個人史を辿っていくと、常に一貫性のある行動をしてきているわけではない。どうしてこんな行動にでたのか?という意外性が面白い。
(例えば高杉晋作は、人間平等の思想を掲げていた。けれども彼のサポート役となっている人と喧嘩した時に思わずその人のことを「このどん百姓!」と罵倒してしまう。)
一本道を歩いたひとよりも、挫折を乗り越えた人や挫折してそのままだめだった人に惹かれる。
●編集者とのやり取り
編集者によって対応は様々。ただ、自身も経験があるため、相手(編集者)が何をやっている(やっていない)のは言わずともわかってしまう。
仕事やってますアピールは好まない。どちらかというとアピールしない人の方が仕事をきちんとやっている。
デザイナーは編集者に選ぶので作家には誰にお願いするのか選択権はない(意見はいうが)
また、デザインを決める仕事は言語で伝えられないものもあり、一発で出来上がるのがベスト。逆に欲しいものと大幅にずれていると何度も修正して行く必要があり、修正し続けていくとぶれていく。
櫛挽道守は漂砂にうたうと同じ方にお願いして作者の意図をくんでもらった。文字組みを一から作ったり、装丁にこだわっている。
担当編集者との信頼関係があって良い作品が出せた。
●野球好き
学生時代はソフトボールに明け暮れた(中学時代は卓球)。常に怒られっぱなしだったが、それにうまく対応していかなければ前には進めない。
ポジションはピッチャーで負けず嫌い。白黒がはっきりしないものははっきりしておきたいタイプ。
現在野球を題材にした連載をしている。(小説新潮:球道恋々)そのため、中断していたソフトボールを再開して、忘れかけていた試合中の些細な体の動きを文に取り入れている。
●編集者時代(木内さんは編集者を経て作家の道に入る)
編集長の指導は厳しかった。
「自分の目と足で歩いて確認したもの以外企画に出さないで。」(なんとなく流行りそうな企画を提出して注意される。)
「あなたに支払うタクシー代はない」(与えられた仕事を終わらせるために遅くまで仕事をしようとしていた時。)
直接質問しにいくよりも、技を盗むタイプ。
周りが怒られているのをみて、とっさにメモをとり後で読み返して頭に入れておく。前もって地雷をふまないようにしていた。(それでも叱られた)
たくさん怒られたけれど、それが今役に立っている。(きちんと叱ってくれる人がそばにいるといい。)
●自ら雑誌を発行した理由
編集者として働いていた1990年後半の音楽シーンはセールスが大きいアーティストばかり注目されていた。仕事では売れている側の記事に注力していたものの、一方でくるりや中村和義、スーパーカーなどの多様な才能が出てきており、そちらに焦点が向けられていないのは残念だった。そこで、気になる芸術家(俳優やアーティストなど)に焦点を当てた雑誌「Spotting」を発行する。
様々な芸術家にインタビューしたことは作家業の人物造形に役立っている。
物語に人を添わせるのではなく、この登場人物がどう行動するのかは自身と登場人物との間のインタビューのようなもので進めている。
※詳細はエッセイ集「みちくさ道中」のなかの「いい気になるな」に書かれています。
●本を書く原動力
・本は答えを書いていない。ある種の考えを提示するだけである。しかし、それが面白い。
・どこまでいっても青天井のない世界である。不安がないわけではないが、それよりも答えが出ないものに対する追求欲が勝る。
●本を読むことについて
・学生時代に「自分の人生は一度しか生きられない」といわれ、ショックを受ける。
例え自分の周りに通じ合う人がいなかったとしても、本の中では出合えることがある。
・語彙の豊かさが表現の幅にもつながる。
あえて割愛した部分がありますが、このような内容だった。
木内さんの人となりについてエッセイ集「みちくさ道中」に書かれているのけれど、いつも怒られてばかりだったという。
作家としてもキャリアとしてはそれほど長いわけでもないのに直木賞を受賞することになり、一斉に褒められた時もいつ怒られるのかびくびくしていたという(普段の木内さんを知らないのでどうしたらそうなるのか全く想像できないけれども)
それでも、その後も着実に良い作品を一つづつ積み上げている木内さんの作品はこれからも読むだろうし、読み返すことになるだろう。
次の出合いを楽しみにしています。